「ずっとわたしの中で生きている。」
葬儀とは、大切な人が永遠に
心の中で生き続けるための儀式。
私たちが大切にしているのは
心の底から寄り添うこと。
ともに想い、ともに、つくる。
草苑
費用・葬儀プラン
皆様のご希望に応じた葬儀の形をご提案します。
※標記価格、写真のプランは一例です。 地域、葬儀場により内容、価格が異なることがありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
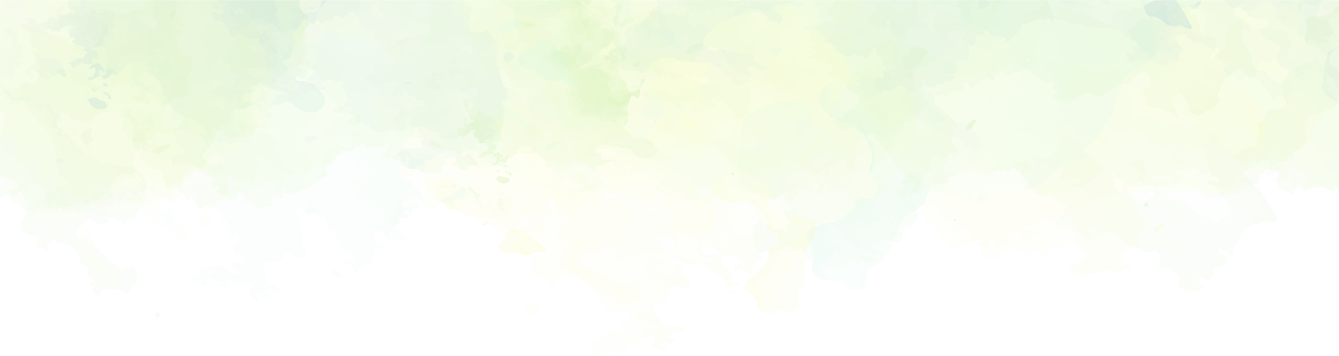
選ばれる5つの理由
私たちがいちばん大切にしているのは、故人さまとご家族に、心の底から寄りそうこと。ともに想い、ともに、つくること。
関わるすべての人に心を重ねて、どこまでも丁寧にひとつのお葬式を、つくりあげていきます。

ご葬儀だけでなく、その前後も私たち草苑が無料でご対応いたします。
ご葬儀の前

お電話でご相談
- 質問や不安の解消
- ご葬儀の費用、場所流れのアドバイス

対面での事前相談
資料をご覧いただきながら、その方に合ったご葬儀を専門相談員が直接アドバイス
ご葬儀

ご逝去〜お葬儀当日
- ご搬送
- ご安置
- ご納棺
- お通夜
- ご葬儀
ご葬儀後

アフターサービス
- 役所手続き、相続のアドバイス
- お仏壇、お墓、供養のアドバイス
- 返礼品の準備
- ご案内がなかった方へのフォロー
お客様からたくさんのご感想をいただいております。
葬儀の基礎知識
一覧を見る
宗教によってこんなにも違う!宗教別の葬儀作法の違いについて
宗派によって、唱言や焼香の回数など様々な作法が異なります。今回、宗派別の作法をご紹介しておりますので、喪主の方は勿論、参列される方も是非ご参考にしてください。 「焼香の回数は何回が正しいの?」とよく聞かれることがありますが、実は、宗教・宗派によって作法が異なります。 今回、宗派別に作法をまとめておりますので、ご参考にして頂ければと思います。 ■唱言 ・真言宗:南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう) ・天台宗:南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ) ・臨済宗:南無釈迦無尼佛(なむしゃかむにぶつ) ・曹洞宗:南無釈迦無尼佛(なむしゃかむにぶつ) ・黄檗宗:南無釈迦無尼佛(なむしゃかむにぶつ) ・浄土宗:南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ) ・浄土真宗(西本願寺):南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ) ・浄土真宗(東本願寺):南無阿弥陀佛 (なむあみだぶつ) ・日蓮宗:南無妙法蓮華経 (なむみょうほうれんげきょう) ・日蓮正宗:南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう) ・友人葬(学会): 南無妙法蓮華経 (なむみょうほうれんげきょう) ・神社神道 :- ・天理教 :- ・金光教 :- ・キリスト教(カトリック):- ・キリスト教(プロテスタント):- ■焼香の作法 ・真言宗:香をいただき3回 ・天台宗:香をいただき1~3回 ・臨済宗:香をいただき3回 ・曹洞宗:いただいて1回、いただかず1回 計2回 ・黄檗宗:香をいただき3回 ・浄土宗:香をいただき3回 ・浄土真宗(西本願寺):1回 ・浄土真宗(東本願寺):2回 ・日蓮宗 :香をいただき3回 ・日蓮正宗 :香をいただき3回 ・友人葬(学会):香をいただき3回 ・神社神道:玉串を捧げる ・天理教:玉串を捧げる ・金光教:玉串を捧げる ・キリスト教(カトリック):献花する ・キリスト教(プロテスタント):献花する ※香をいただくとは? 右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香を少量つまみ、手を返して額の高さまでかかげることを言います。 焼香の回数は、会葬者の人数によって、お寺様から回数変更の指示がある場合もございます。 他にも、宗派によって御礼料の表書きの書き方なども変わります。 ■最後に:お寺様・各派・地域によっては異なる場合があります 今回ご紹介した内容は、あくまで基本のものとなります。 詳しくは自身の宗派元にて、ご確認いただくことをおすすめ致します。
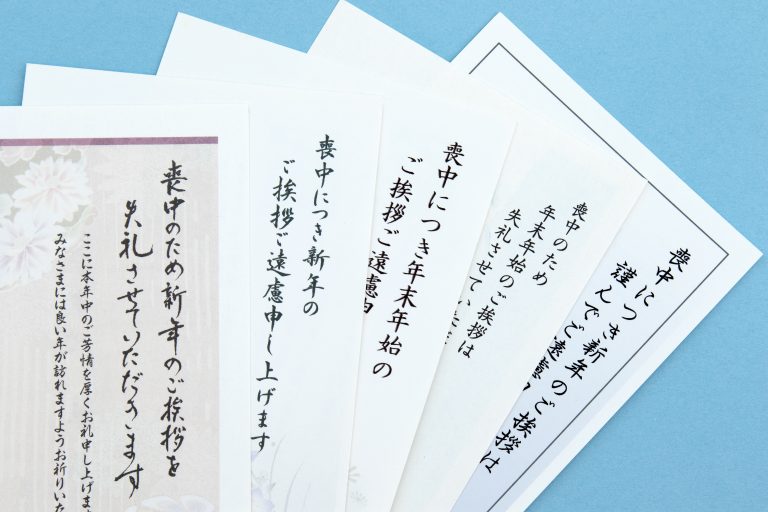
【喪中】祖父母の喪中の時はどうすれば良い?年賀状や結婚式は?
現代人にとって喪中という言葉にもっとも多く触れるのは、年賀状や結婚式にまつわる話題の中でしょう。本記事では喪中の基礎知識に加え、喪中の際に年賀状や結婚式に対してどう取り組めば良いのかを解説していきます。 目次 そもそも喪中とは? 喪中の範囲はどこまで? 喪中と忌中の違い 忌中とは 喪中と忌中の違い 喪中の際の年賀状について 喪中の際の結婚式について 結婚式を挙げる場合 結婚式に参加する場合 まとめ 「いざという時役に立つ」贈儀計画コラムの続きはこちらから

納骨をしない場合の選択肢とは?注意点と併せて解説!
大切な人の死に向き合う中で、重要な供養の一つが納骨ではないでしょうか。辛い別れの中でも「遺骨との別れ」は最後のメインイベントともいえます。従来であれば「お墓に納める」のが一般的と考えられますが、「納骨はしないといけないの?」「いつまでも近くに残したい」と思われる方も多いはず。今回は納骨の基本知識から今までと違った遺骨の納め方まで解説していきたいと思います。 目次 納骨とは 納骨をする理由とは 納骨をしないと法律に違反する? 納骨はしないといけないことなのか 納骨をしないと法律に触れてしまうのか 日本には、墓地、埋葬等に関する法律が存在する 自宅の庭や私有地に墓は建てられない 自宅の庭や私有地の土中に遺骨を埋葬できない 自宅の室内で保管はできる 納骨をしない場合は手元供養 遺骨を入れる骨壺 骨壺は寒暖の差や直射日光を避ける 遺骨を身につけていられるペンダントがある まとめ 「いざという時役に立つ」贈儀計画コラムの続きはこちらから

【手元供養】方法・メリット・供養の種類
手元供養とは、火葬後した故人の遺骨を、自宅など身近な場所において弔う供養方法です。本記事では、手元供養の方法や、分骨して残った遺骨の供養の方法などをご紹介していきます。 目次 手元供養の背景手元供養の方法は全骨安置と分骨安置の2通り全骨安置の場合分骨安置の場合手元供養のメリット・デメリットメリット1.墓が必要ないメリット2.故人を身近に感じることができるデメリット1.自身が亡くなった後の備えが必要デメリット2.周囲の納得を得にくい場合がある遺骨を安置する方法は様々骨壷アクセサリーにする分骨安置で残った遺骨について分骨を行う際の注意点ペットも手元供養にできるまとめ 「いざという時役に立つ」贈儀計画コラムの続きはこちらから


















































